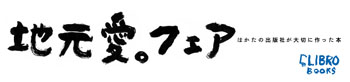前山 光則
最近出版されたばかりの松原新一・編著『丸山豊の声—輝く泥土の国から』(弦書房)、これは実に興味深い本であった。
丸山豊は、戦時中は軍医として南方におもむき、ビルマ方面で死線をさまよった末に帰還する。戦後、福岡県久留米市で医師をしながら詩を書き、「母音」等の詩誌を発行する中で安西均・谷川雁・森崎和江・松永伍一・川崎洋・高木護など、たくさんの才能ある人たちも発掘した。平成元年に74歳で世を去ったが、もっと評価されるべきだと思う。
生前の丸山豊へのインタビューが最初に載っているのが有り難い。丸山は、主知的抒情詩を書く詩人たちとも、それには飽き足りぬグループとも分けへだてなく交流を持ったので、温厚な雰囲気の持ち主でバランス感覚に秀でていたという印象がある。事実、そうだったろう。ただ、基本線ははっきりしている。
「だいたい芸術の道というのは、最初に会った時に、この人は出来るか、出来ないかというのは、おおよそ見当はつきますもんね。ことに処女作をみたら、処女作がハシにも棒にもかからんというのだったら、十年、二十年やっても駄目ですね」
戦争を体験し、人間の卑小さを真底見てきた丸山。それでも、戦後、詩という文学表現へのこだわりをつづけた。バランス感覚の底にあるものは、このとおり厳しいのである。
そして、文芸評論家の松原新一氏が司会を務めての座談会が二つ収載されている。メンバーは陶芸家で詩人の山本源太氏、H氏賞詩人・鍋島幹夫氏、ユニークな作風の詩人・古賀忠昭氏。いずれも丸山豊に師事した人たちだが、それぞれ持ち味がまったく違うので、出席者の顔ぶれ自体が丸山の造り上げていた人間関係を象徴していると言える。松原氏の手際よい司会の下、山本源太氏は物作りの原点に立たせてくれた丸山を「父」のごとき存在だと語る。鍋島氏は丸山の詩「白鳥」を完結した球体である、「夫唱」という詩は二つの中心点を持つ楕円の構造だ、と分析する。そして古賀氏は、丸山宅に住み込んでいたことがある関係もあって、生活者・丸山氏に共感を示す。互いに存分に丸山豊論を展開するが、理屈っぽくなっていないので読みやすい。
中でも特異なのは古賀忠昭氏で、「例えばですね、先生がですね、ふだん話しよんなさっときに急に生まのことばが出て来たとすっですね、ちぐはぐですもんね」、一貫してこんな喋り方をしている。詩集『泥家族』血のたらちね』『血ん穴』等でどろどろした土着の世界を展開した詩人だ。意識して方言表現にこだわっていることは知っていたが、座談会の席でも筑後弁丸出しであったか。文学論をする際に純粋な生まの方言で喋るというのは、これはたいへん魅力的なことではないだろうか。残念ながら4年前に亡くなっているが、丸山豊の周辺にはこういう人もいたわけだ。会ってみたかったなと思う。