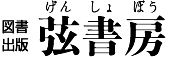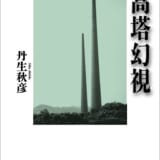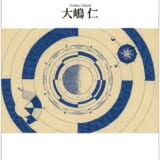2、3日前のこと、友人から、
「淵上毛錢に『蟇多羅』という詩があるですが、最後の行の最初の漢字2文字は、何と読むのですか?」
と訊ねられた。
「ん?」
咄嗟には何のことか分からなかったので、早速、実に久々に淵上毛銭の本を引っ張り出してみたのであったが、ははあ、なーるほど。
蟇多羅
みごとなる憂鬱さで
蟇は老いの身から
かげ深い石塊(くれ)に似た
苔のある孤独を放つてゐた
うす闇の虚空に
つと沈痛の弧をえがき
古代切れのやうな沼を裂いてゆく
その玄妙のすがた
ひくい岸べに皺をのこし
童戯のあゆみに滴をたれ
なれた竹林の根がたで
身ぶるひした
やがて太くひくうく
月を呼びはじめると
村はしだいに眠らされ
あら壁の鎌は鋭く
裏山からの微風に磨かれたが
ちひさなる孤独の城主 蟇(がま)
蟇は目をほそめ
おほきく土を抱いて
いつまでも月に濡れてゐた
屋根の厚いお寺の
棕櫚の撞木がそれを見た
この詩の最後の行に出てくる「棕櫚」の読み方が分からない、というわけである。
「これね、これは、ほれ、シュロですよ」
「へ? シュロ?」
「なんさま、ほら、椰子(やし)に似とる木ですたい。時々、田舎道を行けば、田の畦などにポツンと植えてある。あれですよ」
「ああ、はいはい、シュロの木ねえ」
彼は納得してくれた。
お寺の鐘撞き堂には、必ず撞木つまり鐘を打ち鳴らす棒が吊り下げられている。「棕櫚の撞木」は、そういうことなのだ。
というわけで、一件落着であった。
後で辞典を引いてみたら、「棕櫚」は「ヤシ目ヤシ科シュロ属」だそうである。鐘撞き堂の撞木には、どこでも棕櫚の木が使われるようであり、それ以外の材料が使われている例は見たことがない。だから、棕櫚はよほどに撞木用として向いているのであろう。
さて、そんな次第で、久しぶりに淵上毛銭の詩「蟇多羅」を目にしたのだったが、なかなかに意味深長というか、玄妙というか、味わい深い作品だ。この詩に描かれた蟇は、だいぶん年老いているような気配がある。竹林の根方で、身震いをする。静かなる村の、月が照る夜、そのような中での「孤独の城主」である。彼はたった一匹で村の中に居り、月光の下にさらされている。静謐(せいひつ)な夜の気配が惻々と伝わる詩だなあ、と感心する。
毛錢は寝たきりのままで15年間の闘病生活を送ったのだが、この詩もやはり寝床で書かれたはず。であれば、毛錢は主人公の蟇も、竹林も、沼も、夜空に浮かぶ月も、実際には目にしなかったのではないだろうか。どうも、そう考えられるだろう。
しかし、そうであるのに、「蟇多羅」が醸し出す絶妙の幽玄さはどうだ。読む者はいつの間にか毛錢の描き出した景観に魅了されてしまうはずだ。少なくとも、わたしはそうである。
昭和22年(1947)に出版した『淵上毛銭詩集』には、この「蟇多羅」のすぐ後に次の詩が収められている。
矢車草
女を信じるからよと
その女は言った
ぼくは信じたわけではなかつたが
女は信じてねと云つたのだ
見廻はせば なるほど
女は多すぎる
だが友よ
信じて悪かつた女だつたとは
あんたはとその女は云ふ
あんたは女に甘いのよと
これは「蟇多羅」とはうって変わって色っぽい作品だ。「女を信じるからよ」「信じてね」「あんたは女に甘いのよ」との女のセリフ、ひどくなまなましい。病気に伏してしまう以前の毛錢は、女性遍歴もあったようだから、ここにはそのような彼の過去の残像の一部分が反映されているのだろう。
こうした「蟇多羅」「矢車草」のような作品を、毛錢は30歳になったかならぬかの時期に書いている。「矢車草」には、若者の生臭さが濃厚であり、言うなれば年齢相応の作品と見ることができるだろう。だが、「蟇多羅」の方の雰囲気はどうだろう。30歳前後の年齢にしては、えらく老成しているのではないだろうか。25歳の時から病いの床に伏したままの生活が、かっての生臭かった男をいつのまにかそうさせてしまっていたのかもしれない。
もしも自分が若い時分に毛錢と同じ境遇になってしまっていたら、どういうふうに病床生活を送っただろうか。このように冷静に自身を見つめるようなことは、不可能だったろうなあ、と思う。人間として格が違うなあ、と、感心してしまう。
友人が質問してくれたおかげで、こうして淵上毛銭について久しぶりに作品を読み直し、考えてみることとなった。声をかけてくれた友に、感謝、感謝!