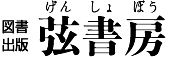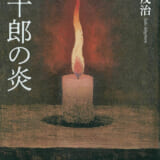前山光則
6月下旬のこと、水俣市在住のM女史から朝早くに電話がかかって来た。
「毎日、蒸し暑かですねえ。こんな時には、寒川(さむかわ)水源にソーメンを食べに行きましょうよ」
「エッ、あ、いやあ、それは良いですねえ!」
いやはや、これはなんとも素敵なお誘いだった。同じ水俣市に住む友人K氏にも声をかけてみたら、
「うん、連絡があった。俺も行くよ!」
彼の方にも、すでに声がかかっていたのだそうだ。
わたしの住む八代市から水俣までは、40キロ余である。その日、まだ梅雨さなかであったものの、たいへん良い天気であった。せっかく出かけるのだから、約束の時間よりもだいぶん早めに家を出て、水俣港あたりをドライブしたり、海岸でぼんやり海を眺めたりしてみた。八代と水俣の間の不知火海はリアス式海岸であり、景色に変化があって愉しいのである。
水俣港の方へ行ってみたら、防波堤に5、6人ほど釣り人が来ていた。皆さん実にのんびりと立ったり腰を据えたりして、竿を振っている。程良い晴空の下、のどかな、良い眺めであった。もっとも、小一時間ほど釣りを見物したのだが、1匹も獲物は挙がらなかった。あれは、どうしたわけであったろう。たまたま釣り場付近に魚群が寄ってきていなかったのだろうか。あるいは、時間帯が良くなかったか。それとも……?
ともあれ、景色が良い。目の前に恋路島がデンと横たわっている。またこの島の名前が素敵ではないか。「こいじしま」と訓(よ)むのだが、人によっては「こきしま」「こぎしま」と呼ぶ場合もあるのだそうで、「こぎしま」の場合は「漕ぎ島」と字を宛てて良いのだという。つまり海岸から近くに浮かんでいる島なので、楽に艪(ろ)を漕いで行ける、というような意味合いがあるのだそうだ。このような謂(い)われについては、かつて石牟礼道子さん等から聞いたことがある。
そして、午前11時、M女史の住む寺を訪ねた。寺にはすでに友人K氏も来ており、すぐに出かける手はずになっていた。わたしの車に御両人とも乗ってもらって、出発した。水俣の町なかから、東の方の山間部へと分け入って行くのである。
水俣は、チッソが垂れ流した水銀混じりの排水により海が汚染され、水俣病が発生したことで広く知られており、「海沿いの町」という印象がどうしても先行してしまう。だが、実際には海岸線から数キロも入らぬうちにはまったくの山間部となるのである。
その日も、町なかにあるM女史の家から発した後、直きに山道へ入った。そして、あちこちに棚田が展開するのを眺めながら、谷あいをうねうねと30分ほど走行したであろうか。もはや、海岸部からまったく離れてしまい、ずいぶんと山深く入り込んで来たような景観だ。実際、そこらはもう球磨・人吉地方や九州脊梁山脈へと続く山岳地帯の一部分なのである。
程なく寒川水源に到着した。
ここに、冷やしソーメンを食わせてくれる「寒川水源亭」という店が開かれている。谷あいのやや平らになった一画にテントが張られ、客席や炊事施設などができているのである。例年、5月から9月末まで営業するのだそうで、わたしたちが到着した時すでに先客が10人ほど来ており、おのおのテーブルに座を占めて冷やしソーメンを愉しんでいた。ただ、広い店内、全体的にはガランと静かな印象だ。なんといってもまだ真夏ではないわけであった。
テーブルの真ん中に丸い水盤が据えられており、スイッチを入れれば中できれいな水がグルグルと回り出し、そこへ冷やしソーメンを投入する。それを箸で掬って取って、次から次に食べるのである。
グルグルと回る水の中からソーメンを摘まみ出し、麺ツユにサッとつけた後、口に入れる。このツユが、干しエビを出しに使ってこさえてあり、たいへんおいしい。
3人とも、しばらくはお喋りするのは忘れてしまうほど冷やしソーメンを啜る作業に熱中してしまった、いや、まったく、おいしいのであった。
「ねえ、お代わりしましょうか」
とM女史。K氏も、ソーメンを頬張ったままで嬉しそうに、うん、うん、と頷いた。もちろん、わたしだって異存はなかった。
冷やしソーメンを啜るだけでなく、お握りが一人につき2個ずつ。ソーメン+お握り2個、考えてみればえらく炭水化物過剰な食事ということになるだろう。でも、なんといってもおいしいのだから、しかたがない。人間、栄養のバランスに気を遣うことは大切、しかし、たまにはこういうふうな愉しみ方をしてみて良いのではないだろうか。
そして、鯉コク(鯉の味噌汁)も注文してあった。これがまた、谷川の水を引いた水槽に泳がせてあったのだと思われるが、川魚特有の臭みがない。しかも、鯉の身の旨みがまったりと充分に伝わってくるのである。こんなおいしい鯉コク、久しぶりであった。
もう十数年前になるが、女房と一緒に東京へ出たついでに長野県へも足を伸ばし、安曇野(あずみの)や小諸(こもろ)方面を廻ってみたことがあった。その折り、信州大学教授の遠藤恒雄という方に会うことができて、川魚料理屋で昼食を御馳走してくださったのだったが、その時のメニューが鯉料理であった。鯉の洗いも鯉コクも、たいへんおいしかったことを今でも鮮明に思い出すことができる。鯉は、ゆっくりじっくり育てられたのであろう、身が、ほんとうにうまかった。鯉こくの汁がまた、味わい深かった。海を持たない地域、信州。しかし、その代わり、川魚についてはおいしく味わうためのノウハウが昔から育まれているのだろうな、と感心したのだった。寒川水源で食事をしながら、久しぶりに長野でのそのような記憶が甦った。
ソーメンのお代わりが来た。3人で、またモリモリ、ツルツル、食べた。お腹いっぱいとなった。うん、実に良い気分であった。いや、ほんとにまことに「炭水化物過剰」であった。
「でも、良かとよ。鯉コクの方に栄養があるからな」
ツルツルとソーメンをすすり込みながら、皆してしきりに言いわけをしてみた。
もう、まったく、お腹いっぱいであった。
この寒川水源亭というところは、住所をいえば「水俣市久木野(くぎの)寒川579」である。背後に大関山(おおぜきやま)が控えており、標高は901メートル。たいして高くもない山であるが、しかし、海辺から入ってじきに山間部になるのだ。海近くの山としては、「深山」と称していいほどに鬱蒼として、まことにどっしりしており、風格が感じられる。ここはその大関山の麓部分に位置し、ソーメン流しに使われる水は四季を通じて14度とのことだ。そのような冷水が、
「このあたりでは日に300トンも湧き出すのだそうですよ」
とM女史が言うから、
「いや、それじゃ、まるで球磨川の水源地と同じだな!」
わたしはついつい声を大にして言ったのであった。
そうなのだ。球磨盆地の一等奥で、九州脊梁山脈のど真ん中、標高ちょうど1000メートルの斜面からドバッと噴き出す球磨川水源、あそこで水の中に手を突っ込んでみるといい。手が痺れてしまうほどに冷たいのであり、20年ほど前に水温計を持って行って計ってみたことがある。その時の水温は10度であった。あそこの水に比べたら、ここのは4度高い水温だ。「水源」とはいえ、さすがに九州脊梁山脈ほどではないわけである。でも、ソーメンの水に手を浸けてみたら、結構冷たい、冷やっこい。やはり草深い山中の渓流水ではあるのだった。
つまりは、ここ寒川水源はこんなに海岸近くにありながら、九州脊梁山脈まっただ中の渓谷に準ずるような状態を健気(けなげ)に保っているわけである。いや、なんだか、不思議な感じだった。貴重な一帯だなあ、と感心したのであった。
2025・7・7