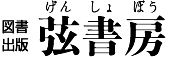前山光則
3月9日、水俣市へ行ってきた。「淵上毛錢を顕彰する会」の集まりに参加するためだった。
その日は詩人・淵上毛錢の命日なのである。毛錢は本名・喬(たかし)、20歳の時に結核性股関節炎を病み、水俣市陣内(じんない)の生家で15年間という長いあいだ寝たきりの闘病生活を続けた後、昭和25年(1950)3月9日、35歳で亡くなっている。
毛錢生家のすぐ近く東福寺の萩嶺強・美保夫妻が「淵上毛錢を顕彰する会」を立ち上げたのは、平成10年(1998)であった。その時は3月8日に集まりが行われて、わたしが東福寺の本堂で「淵上毛錢の詩を語る」と題して講演している。以後は、毎年命日の3月9日にみんなで毛錢の墓に詣でた後、寺で会食しながら詩人の生涯やその作品について語り合うようになったのである。夫の強氏が亡くなられた後も奥様や息子さん、そして水俣在住の毛錢ファンたちによってこの行事は地道に続けられて来た。わたしも、なるべく参加するよう努めてきた。
その日、午後1時にお墓の前に集合とのことだったので、12時40分頃に水俣市役所の駐車場に車を置き、裏手の3号線を5分ほど歩いて左手の山道へ入ると、上の方に墓地が見えている。毛錢のお墓の前には、すでに30人を超えるほどの参加者が集まっていた。『食べて祀って――小さな村の祭りとお供え物』(弦書房)の著者・坂本桃子さんや、最近写真集『ここで眺める水俣――あとから来る者たちの場所』(弦書房)を出版した森田具海(ともみ)さん、京都からやってきて石牟礼道子さんの旧居で古書店カライモブックスを営む奥田順平さん等、若い人たちも来てくれていた。
主催者側からの挨拶があり、読経が行われ、やがて順々にお詣り。そして、東福寺まで移動するのである。
山を下りようとするとき、墓の前から水俣市内を眺め渡してみた。毛錢の詩に「寝姿」というのがあるが、
流れには 奥山の雪がにほひ
ゆふべの石に 魚は眠り
まつ暗いなかに
鉄橋だけは 待つてゐた
やがて 夜行列車の窓から
たらたらと 蜜柑の
しぼり汁のやうな灯が
魚の寝姿のうへに
宝石の頸飾りとなつて落ちた
魚は 眠かつたが
もういちど ゆつくり
寝床をかへてみた
頸飾りはすぐ消えた
この詩に書かれている「流れ」つまり水俣川も、鹿児島本線(現在の肥薩おれんじ鉄道)の走る「鉄橋」も、そして「奥山」の姿も、墓地に立つとすぐさま目に入ってくる。ここはまことに眺望に恵まれた場所だよなあ、と、訪れるたびに感心する。
東福寺へ移動し、懇親会が始まった。色いろのおいしい御馳走や飲み物が用意されており、楽しい集いである。
墓地へお詣りに行ったメンバーに加えて、「合唱団みなまた」の人たちも来てくれた。そして、毛錢の詩「なんとなんとなんしょ」他、3曲ほど唄ってくれ、聴いていて気持ち良かった。
川ん中けおつとは
なんとなんとなんしよ
あたればじく(利巧)さん
あたらんば馬鹿たん
びな(貝)に だくま(えび)
おどもんげぐら(小魚)
釣つても掛からん
えど(餌)かすつてはつてた
正月どんのこらつ(来)せば
なんとなんとなんしよ
あたればじくさん
あたらんば馬鹿たん
ひや(冷酒)にかずの子
もちに砂糖
濁酒、吸物ん
そらさぞうまかろ
倉ん中けあつとは
なんとなんとなんしよ
あたればじくさん
あたらんば馬鹿たん
菜つ切り包丁
菜つ包丁
垂木のつばめん巣
知つとるしこ言うた
そらまた御意ね
「なんとなんとなんしよ」は、人の心を和ませてくれる詩だ。水俣弁がたいへんうまく磨かれた上で使われており、軽快で、童心に帰ったような気分にさせてくれる。
この詩、いつごろ書かれたのか分かっていないが、どうもはじめから曲がつくのを前提にした上での作だったのではないだろうか。「昭和41年6月滝本泰三作曲(カワイ合唱名曲選)混声合唱組曲『小さき町』に初出」と国文社版『淵上毛錢全集』には記載されている。つまり、死後ずいぶんと時間が経ってから活字化されたことになるわけだが、音楽家の滝本とは親友といっていいほどの仲だったそうだ。作品が成立する時点で、すでに、この詩に曲をつけることは両者の間で意識されていたのではないかと思われる。
昼食会では、わたしにも何か淵上毛錢について喋るように言われた。それで、ちょっとだけ語らせてもらったのだが、「なんとなんとなんしょ」は25行の詩であり、毛錢の作品の中では長い方だ。このリズミカルでテンポ良い作品の裏側には、えらく上機嫌の作者がいるように思える。そう、つまり、体の状態が比較的落ち着いている時、詩人は和やかな気分で饒舌になることができていたのではないだろうか。ちなみに、もっと長いのでは、「冬の子守唄」は48行、「きんぴら牛蒡の歌――暮景参面菜根賦―其壱」が40行、「無言歌」が59行、「ばか貝のばか貝の歌」は44行、「人參微吟――暮景参面菜根賦―詰」が42行である。
しかしながら、この人にはいったいに至って短い詩の方が多いのである。それを、どう捉えてやれば良いか。
たとえば、「春の汽車」という題の作品などは、初めは、
春の汽車は遅い方がいゝ
おーい
その汽車止めろお
と言つて見ようか
春の汽車は遅い方がいゝ
とされていた。鹿児島本線を遠望していての作ではないだろうか。毛錢の住んでいた家からは、確かに鉄道が眺められるのである。さて、この詩であるが、毛錢は推敲に推敲を重ねた果てに、後では、
春の汽車はおそいほうがいい。
このたった1行にしてしまっている。
考えてみれば、「おーい/その汽車止めろお/と言つて見ようか」の部分は、作者の上機嫌さが反映されてはいないだろうか。毛錢は、それを後に削ってしまったわけである。思えば、機嫌の良さは得てして冗漫さを生む。毛錢は、多分、そうした弊を嫌ったのだ。しかも、「遅い方がいゝ」の部分は「おそいほうがいい。」というようにひらがなだけで記されており、これは多分意識的にそうしたかったのではないかと思われる。
つまり、毛錢の作品に短いものが多いというのは、やはり、一つには徹底して推敲を重ねた。そして、自身にとって余分にしか思えぬものは削ってしまうことで詩としての高い完成度を目指したのではないだろうか。
さらに、もう一つ、詩人の体力の問題もあったに違いなかった。結核菌が、少しずつ確実に詩人の体を蝕んでいったのである。長いものを書こうにも、徐々に体力が落ちて行ったかと思われる。だから、機嫌良い状態で冗漫さを愉しむ余裕はなくなっていった。そう言えば、毛錢は俳句も結構詠んでいるのだが、五・七・五という短い詩型は疲れなくて済むので、病人には向いていたかも知れなかった。
毛錢は、午前8時10分に亡くなったそうだ。その前、午前5時頃には、
貸し借りの片道さへも十万億土
と口ずさんで、これが辞世の句となっている。体力の絶望的な限界に達した詩人が、最後の最後に発した「一行詩」であり、辞世句だったのである。
――ザッとそのようなことを皆さんの前で語ってみた次第であった。
来年もこの会は催されるはず。必ず出かけるつもりだ。
2025・3・25