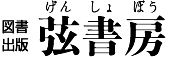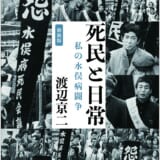前山光則
いつぞやも書いたように、日奈久(ひなぐ)温泉によく行く。常々、町の中心部にある「温泉センターばんぺい湯」を利用しており、入浴料は500円と高いが、身体障害の人や高齢者は310円で入らせてくれるからありがたい。たまには贅沢して、幸ヶ丘という老舗旅館の内湯に入らせてもらう。ここは500円である。そして200円で入浴できる銭湯も2軒ある、といったふうで、日奈久ではそれぞれの湯が楽しめるのである。
昨日は幸ヶ丘に行った。ここは、まったくの源泉掛け流しである。大きな鯉の形をした湯口から、純粋混じりっけなしの湯がどんどん噴き出てくる。じっくり、ゆっくり、体を温めたが、なんとも気持ちよかった。そして、湯から上がり、着替える時、不意に「竹輪が食いたい」と思った。うん、今日は晩飯のおかずに竹輪があると良いな、それも、ムシャムシャと丸囓りしたい。ぜひ、そうしよう! 日奈久という町には、昔から竹輪を製造販売するお店が何軒もあって、店先で製造の実際が見られたりもする。なんだか、よその町に売ってあるのよりも歯ごたえが良くて、おいしい。原材料はスケソウダラとかエソ等だそうだから、地元で捕れるようなものではなくて、どこからか冷凍物の魚肉を仕入れるのである。だが、昔から日奈久といえば竹輪が名物、やはり製造するにあたっての基本的ノウハウがよそとは違うようである。だから、時々買って帰るのだ。
夕食の時、竹輪一本をそのまま食った。うん、やはり良いなあ、と思う。気のせいかも知らぬが、竹輪は、下手に調理したり切り刻んだりするよりも、このようにして丸ごと囓るのがおいしい。焼き上がった時の芳香がまだほのかに残っており、そして、シコシコした歯ごたえ、噛めば噛むほどじんわり感じられる旨み、気持がやんわりと和むのだった。
思えば、わたしなどは戦後すぐの頃に生まれた「団塊の世代」である。少年の頃、竹輪は滅多に食べられぬ贅沢品であった。
学校にいつも弁当を持って行っていたが、おかずが物足りなかった。わが家は母が美容院をしていたたために仕事が忙しく、台所の色んなことは祖母がやってくれていた。祖母は、やはり昔からの習慣が染みついている人なので、万事古風であった。料理について言えば、なにかにつけて根菜類の煮しめを作っていたものであった。家に居るときは、家族みんなで煮しめをおかずに食事すれば、それはそれで愉しかった。しかし、これが、弁当のおかずとして入れてあるのだった。
煮しめの入った弁当は、わが家の場合、いつもよりは見栄えのいいものであった。というのも、常々、弁当のおかずは漬物が並べてあることが多かった。大根や人参の味噌漬けとか、高菜漬け、といった具合である。漬物以外には、前日の夕飯の残りもの。兄やわたしが川で魚を捕らえてくれば、それを煮て弁当のおかずとして入れてあった。なんだか、教室で弁当箱を開く時、気が引けてしかたがなかった。
わたしの通った小学校は人吉市の町なかにあったので、商店街の子たちが多かった。すると、彼らの弁当箱にはおいしそうな惣菜が入っているのであった。卵焼きとか、肉類を煮たものとか、ハム、ソーセージとか、実においしそう。しかも、白御飯にはふりかけで色づけしてあったりして、まことに愉しそうだった。それに比べて、わたしの弁当は、飯には麦が混じっているから、はじめっからなんとなく見栄えが良くない。そして、隅っこの方に漬物、たまに根菜類の煮しめ、といったふうだ。時折り蒲鉾とか竹輪の煮たのが入れてあることがあって、その時は少し嬉しかった。ただし、それは、母が花嫁の髪を結ったり婚礼衣装を着付けしてやる仕事で、結婚式場に出かけて行くことがあった。そんな折りには御馳走をみやげに持って帰るので、翌日、わたしたちの弁当箱もその御馳走の蒲鉾、竹輪類の煮直ししたものが入れてあって、いつもより豪勢にはなるのであった。
そんなわけで、蒲鉾とか竹輪はまったくの贅沢品、普段は滅多に口にできない御馳走であった。
あれは、小学何年生の時だったろうか。親に連れられて映画を観に行ったのであったが、竹輪製造業の家が出てくる物語だった。父親と母親が、まだ夜の明けぬうちから早起きして竹輪を作る、子どもが起きる頃にはたくさんの製品ができあがり、両親はあちこちへ配達に出かけるのである。
そして、その家の息子は小学校に通うのだが、彼はたいそう従順で素直な子だ。それは、つまり、両親とも気が優しくで自分を可愛がってくれるからなのだ。だが、一つだけ彼は癒やしようのない不満を持っていた。
それは、いつも弁当のおかずにわが家の製品つまり竹輪が入れてある、ということ。彼は、常々、家で、竹輪を食わされてばかり。心の底から飽き飽きしているのであった。しかも、弁当にまで竹輪が入れてあるので、これがなんとも恨めしい。ああ、彼にとって、夢も希望もない竹輪弁当! 学校にいて、昼御飯の時間がやってくる。教室で、みんなが弁当箱を広げて愉しそうに食べる。だが、彼だけは自分の弁当箱を覗かれたくないから、校舎の外へ飛び出して、木陰に一人座り込む。そして、誰にも見られないように弁当箱を左手で覆い隠した上で、こっそりと竹輪入りの弁当をさびしくつつく、という暗ーい生活が続くのであった。
スクリーンの前で、田舎小学生のわたしは羨ましくてしかたがなかった。ああ、ああ、自分も竹輪屋の子として生まれたかったなあ。毎日、いやというほどあのおいしい竹輪が食べられるのだ、なんというゼイタクな、分限者(ぶげんしゃ)みたいな生活。あれはきっと、焼き上がる時には良い匂いが家中に漂うはず。まるごと囓れば、しこしこと噛めば、あの歯ごたえ。食べたいなあ。
ああ、それなのに、それなのに、スクリーンの中のバカタレ息子は、竹輪が入った弁当をやたらと恥かしがっている。昼御飯の時間には教室から抜け出し、校庭の片隅、誰もいない場所へと入り込んで、こっそりと食べるのだから、何という親不孝な息子だ!
それが、である。映画のエンディングでは、ある日、彼がいつものように独り密かに校庭の隅っこに行って弁当箱を開けた。すると、顔がパーッと明るくなった。おかず入れには、何と、程よい色合いの卵焼きが敷き詰めてあるではないか! 少年は目を輝かせ、弁当箱に蓋を被せた。そして、クラスのみんなに自分のおかずを見せびらかしたくて意気揚々と教室へ戻って行くのであった。
映画館でそのシーンを見上げていたわたしは、なんだかひどく腹が立った。竹輪屋の息子の気持ちが、まったく理解できなかった。家が竹輪製造販売業を営んでいるということ自体、憧れてしまう職業だ。毎日、あのおいしい食べ物を造っている人たちなんだ! だから、彼もしょっちゅう竹輪を囓ることができる。なんという羨ましさ。しかも、弁当のおかずにも竹輪。何の不自由もない毎日なんだろう。
だけれども、彼はなぜだか弁当箱に竹輪が入っていると嫌がってしまう。そんな自分勝手な子って、許せん! 竹輪にうんざりしているなどとは、ゼイタク病だ。――少年のわたしは、映画の中の竹輪屋の息子に心の底から憤りを覚えた。
しかも、弁当箱の中にある日入っていた卵焼き。少年は目を輝かせ、弁当箱に蓋を被せた。そして、クルリと身を翻し、教室へと戻って行く。顔をクシャクシャに緩めて、だ。
今もって鮮やかにそのシーンが甦る。あの頃、竹輪という食べ物に心底から憧れ、羨ましがっていたのだなあ、と、少年の頃の自分自身が懐かしく、愛(いと)おしくなってしまう。
日奈久温泉界隈の竹輪は、店によって味わいが少しずつ違う。固めのものもあれば、柔らかいのもある。塩味がやや目立つのもあるし、あっさり味もある。だが、総じていえるのは、はじめに記したとおり、どの店の製品もよそで売ってある竹輪よりうまい、ということ。これには、正直なところ、常々感心している。だから、よそへ出かける時に土産品として持って行くことしばしばである。地元で捕れた魚を使うわけでなく、所詮は冷凍物を大量に仕入れた上での竹輪作りであろう。それなのにおいしいのであるから、やはり製造する際の技術的なノウハウというか、レベルの高さが伝統的にあるに違いないと思う。
ああ、竹輪。まことにおいしい食べ物なのである。
2025・4・15