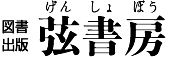前山光則
前回、寺山修司氏についてちょっとだけ触れたが、この人はほんとに多才だったと思う。短歌や俳句や詩・エッセイ・小説・戯曲というふうに多面的に活躍した人だ。
わたしたちが学生だった頃には、前衛劇団「天井桟敷」を率いており、あちこちで上演活動を行っていた。唐十郎の「状況劇場」と盛んに競い合っていたものである。だが、わたしは不思議とこの人の演劇活動に興味を持たなかった。なんといっても俳句と短歌作品が心に沁みた。だから、前回、まずは俳人としての寺山修司氏に触れてみたのである。
そして、今回はひとつこの人の短歌を読み直してみたい。
『寺山修司青春歌集』(角川文庫)という本が出ており、この人の短歌作品のほぼ全貌を知ることができる。巻末に作家・中井英夫が解説を書いていて、それによれば「寺山修司は十二、三歳のころに作歌を始めたらしい」とある。寺山氏の短歌が初めて世に現れたのは昭和29年(1954)、18歳の時だったそうであり、以後、丸16年ほど「公的な短歌の制作発表が続いた」のだという。さて、ではどのような短歌を詠んだか。
夏川に木皿しずめて洗いいし少女はすでにわが内に棲む
煙草くさき国語教師が言うときに明日という語は最もかなし
亡き父にかくて似てゆくわれならんか燕来る日も髭剃りながら
麦藁帽子を野に忘れきし夏美ゆえ平らに胸に手をのせ眠る
青空はわがアルコールあおむけにわが選ぶ日日わが捨てる夢
飛べぬゆえいつも両手をひろげ眠る自転車修理工の少年
樅の木のなかにひっそりある祭知らず過ぐるのみ彼等の今日も
「初期歌篇」の中から引いてみたが、どれも十代の作品と思われる。この人は、どうも、最初から高いレベルの詠法を身につけていたのではないだろうか。
1首目、川の中で木皿を洗っている少女への好意が詠われているのだが、この少女は「すでにわが内に棲む」と言っている。うまい言い方ではないか。すなわち、作者は、この少女に熱い好意を示しているのである。同じく女性への気持ちを表しているのは4首目だ。夏美という女性は「初期歌篇」にしばしば登場するのだが、その娘が麦藁帽子を野原に忘れてきてしまったため、今、彼女の手にはない。彼女は帽子を持たぬ手を自分の胸に載せて眠っているわけだ。一人の少女の可憐な姿が詠まれているのである。
2首目は、この国語教師、「煙草くさき」人だ。つまりこれは作者の批評であり、教師への作者なりの評価が分かるだろう。「明日という語は最もかなし」、そうである。この教師が煙草をくゆらせて「明日」を語る、それは作者にとって矛盾を抱えている大人の姿なのだ。「明日」を語るには、「?」印がつきそうなものでなかったろうか。
そして、3首目。この人の父親は、昭和20年、セレベス島というところで亡くなっている。特高警察の刑事だった由だが、その年、寺山修司はまだ9歳だったことになろう。
5首目はいかにも青春まっただ中にいる少年の歌だ。そして、6首目も7首目も、それぞれ高校生としては出来上がりすぎている。なんといっても、天才肌だったのだ。
言い負けて風の又三郎たらん希いをもてり海青き日は
胸冷えてくもる冬沼のぞきおり何に渇きてここまで来しや
轢かれたる犬よりとびだせる蚤にコンクリートの冬ひろがれり
ノラならぬ女工の手にて噛みあいし春の歯車の大いなる声
マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや
麻薬中毒重婚浮浪不法所持サイコロ賭博われのブルース
さむき川をセールスマンの父泳ぐその頭いつまでも潜ることなし
わが家の見知らぬ人となるために水甕抱けり胸いたきまで
うしろ手に春の嵐のドアとざし青年は已(すで)にけだものくさき
やはらかき茎に剃刀あてながら母系家族の手が青くさし
そして、大人となってからの作品、なんだか才気が迸(ほとばし)り出ているとは思わないか。1首目には宮沢賢治の童話に出てくる「風の又三郎」が、4首目にはイプセンの戯曲「人形の家」の女主人公「ノラ」が引き合いに用いられており、寺山の素養の程が表れている。才気溢れる青年は、たくさんの先行文学を読んで、取り入れ、独自の表現を自身で編み出しているのだ。2首目は、冬の沼地を訪れた自身を「何に渇きてここまで来しや」と自問する。青春のさなか、癒やしようもない心の渇きがここにはある。
それにしても、独特の発想が溢れているわけで、3首目で轢かれた犬から蚤が飛び出すのだが、そこから「コンクリートの冬」が広がったというのだ。なんというイメージの豊穣さ! 6首目から10首目までの作も、1首1首がユニークな寺山ワールドと呼びたくなる。
だが、多分、極めつけは5首目である。「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」、煙草を吸うためマッチに火を点ける。ほんの一瞬そこには光りが灯るのだが、海を覆う霧の深さを前にしてそれは辺りを明るくしてくれるものとはならない。マッチの火のはかなさ、それはまた自らの生きる世界には頼るべき確固たるものがない、との苦い自覚なのである。だから、「身捨つるほどの祖国はありや」と呟かざるを得ない。自分には、信ずべき祖国ってあるのか? これは戦中・戦後を生きた人間が発した、癒やしようのない心の渇きだったのではないだろうか。寺山修司の短歌作品の中で最も秀逸、というよりも戦後短歌の中でも突出した象徴的一首だと思う。
大工町寺町米町仏町老母買ふ町あらずやつばめよ
新しき仏壇買ひに行きしまま行方不明のおとうとと鳥
間引かれしゆゑに一生欠席する学校地獄のおとうとの椅子
たつた一つの嫁入道具の仏壇を義眼のうつるまで磨くなり
村境の春や錆びたる捨て車輪ふるさとまとめて花いちもんめ
そして、この五首、作者は思いきり意図的に土俗的というか、おどろおどろしい世界を詠ってみせている。1首目、「老母」は売りに出されていることになるが、つまりは一首全体がフィクション化されているのである。作者の実際の母親からすれば、こんなふうに歌に「老母」が使われているのでさぞかし困惑したことであったろう。2首目・3首目も同様だ。弟は「行方不明者」だったり、「間引かれ」たりしている。これはもう、おどろおどろしい物語化が行われているのである。さらに、4首目「たつた一つの嫁入道具の仏壇を義眼のうつるまで磨くなり」と、5首目「村境の春や錆びたる捨て車輪ふるさとまとめて花いちもんめ」、2首ともリアリズムとはかけ離れた短歌世界、大胆な虚構を加えて物語られており、これはもう見事というほかはない。
世の中に歌人はたくさんいるだろうが、このような豊穣を発散し得た者が今までいただろうか。いなかった、と言えるし、またこれからも出てこないのではないだろうか。そのようなユニークな逸材に、若い頃にほんの数回、しかもちょっとの時間だったものの、会えた。もっと詳しく話を聞いてみるなら良かったろうが、それにしても実物に対面することができたのである。溜息が出るほどに良い思い出だったわけだ――と、自分ではそう捉えている。
2025・9・1