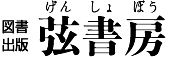このコラム第460回の中で、寺山修司氏の俳句、
林檎の木ゆさぶりやまず逢いたきとき
を引用したのだが、「林檎」、これは北国・青森県の名産といって良いだろう。
手もとにある『寺山修司詩集』(ハルキ文庫)巻末の年譜によれば、寺山氏は、生まれたのは青森県弘前市である。5歳の時に、警察官だった父親の転勤により同じ県の八戸(はちのへ)市へ引っ越す。だが、その年の内には父親が出征したため、残された母子は青森市へ転居したそうだ。そのように青森県育ちなので、小さい頃から林檎にはしっかり慣れ親しんでいたろうと思われる。
わたしは、平成25年(2013)10月に女房と共に東京へ出かけた際、青森県まで行ってみたことがある。そして、あの地方の林檎の多さにすっかり圧倒されてしまった。
10月16日、弘前(ひろさき)市で宿泊し、翌17日の朝、外へ出てみたら青森地方の名峰・岩木山に白く雪が被っていた。10月中旬に、標高・1625メートルの山がすでに雪化粧しているわけだから、やはり北国なのだなあ、と感心した。そして、鉄道に乗り、五所川原(ごしょがわら)で乗り換えた後、金木町へ向かったのだが、その間、窓の外には林檎畑がずーっと広がっていた。自分で「途中、リンゴ畑がつづく」と日記に記しており、とにかく列車の行く手の右も左も林檎畑が続いているなどというのは、九州の人間にとって珍しくてたまらぬ風景だった。
その時は、金木町に作家・太宰治の生家「斜陽館」を訪れてみたのであった。「殿さまの家という感じ」と日記に書いており、堂々たる入母屋造り2階建ての木造洋館はたいへん印象深かった。
そして、その日も弘前市内に泊まり、18日、弘前城址を歩いてみた。ここは、城跡のすぐ傍に「相良(さがら)町」がある。そうか、ここは相良清兵衛(さがら・せいべえ)ゆかりの地なのだ、と目を見張った。実は、わたしのふるさと人吉で相良清兵衛といえば、今でも知られている人物だ。清兵衛は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて人吉藩の家老として大いに辣腕をふるったのだが、あまりにも有能であったため反感を買ってしまった。そして、陰謀により失脚し、遠い北国のここ弘前へと追放されたのだった。だが、有能であったから、弘前の津軽藩でも取りたてられて大いに活躍したという。だから、この人の名が町名となって残されているのである。
そのようにして、青森県では太宰治の生家や弘前城址や相良町等いろいろ見て回ることができたが、でもやはり何と言っても林檎の多さにすっかり圧倒されてしまったのだった。車窓から見た林檎畑だけでなく、弘前市内や青森市で街を歩くと、野菜・果物を売る店先には必ず赤い果実が溢れていた。言うなれば、青森県は一大林檎王国なのだ。あちこちの店先に転げ出さんばかりに林檎が山積みされている光景は、いやはや、なかなかに賑やかな眺めであった。
思えば、小さい頃、卵と林檎は滅多に口にすることができない特別な品物であった。両方とも、風邪をひいて元気をなくしてしまった時だけ、親が「精がつくように」と特別に与えてくれた。卵は、卵焼きをこさえたり、あるいは生卵を炊きたての米飯に混ぜて、「卵御飯」にしてくれた。そして、林檎の方であるが、これは皮を剥き、それを下ろし金で摺(す)って、「はい、これを飲まんばんよ」と、丼に入れて出してくれた。卵も林檎も、病人の体力を回復させるための貴重な「滋養剤」として大切な役割があったわけだ。
林檎は、しかし、青森県のような北国だけで得られる果物ではないようだ。そうしたことは、成長するにつれてようやく知ることになったが、まず東京に出て法政大学の二部つまり夜間部に入った時、長野県出身のクラス仲間から林檎をたくさん貰って、すっかりたまげてしまった。
「長野県でも、この、林檎が、できるわけ?」
と目を丸くして訊ねたら、
「ははは、そりゃあ、君い、できるよ、長野のあっちこっちで林檎は栽培されているんだから」
そんなこと常識中の常識だろう、君は知らなかったのか? とでも言いたげな顔つきで相手は答えたものである。
要するに九州のド田舎からノコノコと出て行ったわたしは、日本国内の色んなことについてまったく知らなかったわけなのだった。
そして、林檎に関する知識は、それ以後も増えなかった。
島根県の津和野町へ友人たちと小旅行を愉しんだのは、もうすでに60歳を越えてからであったが、あの辺りにも林檎畑が散見されてたまげた。へー、こういうところにも林檎が栽培されているのならば、別に北国特有の果物でもないのかなあ、と、なんだかとても不思議な感慨が湧いてきたものであった。
いや、ほんとにそうなのだ。わたしのふるさと球磨・人吉でも、実は、林檎栽培はなされている。『彦一頓知ばなし』や『それからの武蔵』等を書いて大正時代から昭和30年代にかけて活躍した作家・小山勝清(おやま・かつきよ)が、若い頃に『或村の近世史』というたいへん面白い本を書き遺している。大正14年(1925)に至上社という出版社から出た本だ。長らく絶版になっていたのだが、これが、平成6年(1994)になって作家の故郷・相良村によって復刊された。その本に、村の中にあった林檎の木のことが出てくるわけである。
「此地方は、全く、リンゴはみのらぬと云うに、此処のだけは、不思議にも、大きく枝を張り、秋になると、枝一ぱいに、真赤な実をつけた」
そう、これは熊本県球磨郡相良村の四浦(ようら)という集落だが、そのような山間部に、大正時代、林檎の木があった。秋になると、「枝一ぱいに、真っ赤な実をつけた」のである。そして、『或村の近世史』では、たくさん実っていた林檎が、9月17日の夜、ごっそりなくなってしまった。すなわち、「事件」が生じたのであった。実は、その9月17日であるが、村では昔からその日は「盗人晩と名づけられた不思議な一夜」だったわけだ。
「其夜にかぎつて、野菜や果物を、自由に盗むことが許された。まさか大人は手を出し兼ねたが、子供達は盆や正月と同じように、其夜を待ちこがれたものである」
実に、小山勝清の生まれ育った相良村四浦というところは、そのような習俗を色濃く遺していたムラだったわけである。作家は、自らを育んでくれた地域がこんなふうな興味深い人間の営みを続けているということに気づき、『或村の近世史』の中に書き記したのだった。
つまり、林檎が北国の産物というようなことは、実はずいぶん昔から意味のない思い込みでしかなかったことになる。わがふるさとにも、林檎はかなり以前から小規模ながら栽培されていたわけである。
そういえば、10年ほど前であったか、人吉市から東隣り錦町(にしきまち)へ行く途中、国道219号線沿いにかなり広い林檎畑を目にしたことがある。その時は、いやあ、球磨・人吉にも本格的な林檎農家が現れたか、と、とても興味深く眺めたことであった。ただ、その林檎畑は程なくして消えた。現在は、その名残すら分からない景観と化しているから、やはり九州で林檎を育てても、さほど商売にならなかったのであったろうか。
でも、良いや、とわたしは思う。林檎って、津和野やふるさと球磨・人吉に育ってくれても構わないけれど、やっぱり北国の方が似合っていると思う。林檎を囓りながら、遠い、雪の多い地域のことを夢想する、これが愉しい。自分としては、林檎はいつもそのような果物であってほしい。
そして、思えば、林檎を唄った流行歌、これが第二次大戦後の日本にいち早く明るい話題を与えてくれたのである。つまり、戦後の日本で真っ先に流行した歌は「リンゴの歌」だったという。
赤いリンゴに唇よせて
だまって見ている青い空
リンゴは何にも言わないけれど
リンゴの気持ちはよくわかる
リンゴ可愛いや可愛いやリンゴ
作詞・サトウハチロー、作曲・万城目正、唄ったのは並木路子。敗戦直後の日本にいち早くこの歌が流れて、大流行したのだそうだ。昭和22年(1947)生まれのわたしたちも、少年の頃さかんに口ずさんだものである。歌っていて、たいへん愉しかった
あの娘(こ)よい子だ 気立てのよい娘
リンゴによく似た 可愛い娘
どなたがいったか うれしいうわさ
軽いくしゃみも トンデ出る
リンゴ可愛いや 可愛いやリンゴ
林檎って、赤くて、丸くて、おいしくて、みんなから好かれた果物だったわけだ。だけども、九州島のほぼ真ん中にあっては普段はあまり食べることができず、たまにカゼひいたときなどに恭(うやうや)しく摺り下ろしたものにしかお目にかかれなかった貴重品。だから、自分自身、世の中には柿やら梨やら果物があるのだが、林檎に対してはちょっと「別格」としかいいようがないイメージが今でもつきまとう。
これからも何かにつけて林檎は大切に囓りたいもんだ、と思う。
2025・11・4