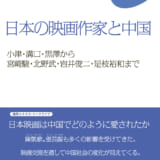前山光則
雨の多い時季となった。湿っぽい日が続くのは鬱陶(うっとう)しいが、その代わり家にいて本を読む時間は増えている。
最近読んだ本で、武井弘一(たけい・こういち)著『琉球沖縄史への新たな視座』(弦書房、FUKUOKA U ブックレット⑳)は興味深かった。この本の中の「琉球沖縄史を見る眼――新たな視座を求めて」は、2020年(令和2)7月26日に福岡市で行われた講演「琉球沖縄史を見る眼―なぜ『茶と琉球人』を書いたのか?―」(福岡ユネスコ協会 主催)がもとになっているのだという。それと、巻末に「新崎千代――人吉球磨に生きた沖縄女性」というのが載せてあるのは、日刊人吉新聞に連載されたものだそうだ。
本書前半「琉球沖縄史を見る眼――新たな視座を求めて」の方は、武井氏の著書『茶と琉球人』(岩波新書)に書かれていることと重なっている。わたしはこの本が出た時、平成30年(2018)2月25日付けの西日本新聞に書評を執筆した。その書評文をここに再録すれば、次の通りである。
「琉球」つまり沖縄県方面で「茶」といえば、普通にはサンピン茶が想起されるだろう。だが、本書に登場するのは熊本県の球磨・人吉地方の山茶である。焼畑耕作をしたあとに自生するのが山茶だが、香りが強くて味も良い。近世後期頃から琉球の人たちは、これを「球磨茶」と呼んで親しんだのだそうだ。
琉球弧については海洋に囲まれた中での交易や漁業中心の生活を思い描きたくなるが、そうではないのだという。著者によれば、近世の琉球は農業を土台として社会が自立していた。琉球は独立した国家であった。だが薩摩から侵攻され、中国とは君臣の関係を結ばざるをえなかった。強い勢力の間に挟まれての貿易は赤字だったが、そのような中で琉球国は農業を奨励し、農村の確立を目指したのである。稲作を推進するための河川改修等が盛んになされている。もっとも農民の主食はサツマイモで、日本本土より一世紀以上も前に琉球に広まっていた。サツマイモの植え付けは年に九回も行われていたそうだ。肥料などほとんど自給できており、「コイ、フナ、ウナギ、タニシといった、水田とその周辺に生息する魚介類も食されていた」、このような食生活も「農業を土台として社会が成り立っていたことを示している」と著者は説く。そして琉球ではもともと茶は嗜好品として飲まれていたが、球磨茶は従来の薩摩・中国からのものよりも口に合うため薩摩を介して購入し、愛飲されたのである。著者は、茶と琉球人との関係を研究してみた末、結局このような「琉球農業国家」という視点に辿り着いている。交易の難しさに苦しみつつ、農業国家の道を歩んだ琉球、読み進めつつ目から鱗が落ちる思いだった。
著者は、球磨・人吉地方で幕末の頃に起きた大規模な一揆には山茶の専売問題も絡んでいたし、先の第二次世界大戦の際に沖縄県からたくさんの児童たちが同地方や近隣に疎開し、苦労したという事実にも言及している。琉球と球磨茶の流通史を辿ることは、こうした底辺の問題に光を当てることでもあったのだ。
とにかく、『茶と琉球人』にはこれまで沖縄地方について抱いていたイメージを根底から覆されるような視点が示されており、感服した。何よりこれまでの蒙(もう)を啓(ひら)かされたのは、このたびのこの『琉球沖縄史への新たな視座』でも分かりやすく説かれているように、近世琉球が「農業」を基本として土台がしっかりしていた、ということ。今まで琉球といえば、わたしの頭の中は「海洋に囲まれた中での交易や漁業」に偏りがちだったのである。あちらへは、沖縄本島だけでなく石垣島や与那国島などの八重山諸島へも幾度も出かけたことがあるというのに、あまり農業方面から琉球・沖縄を見てみるようなことはしていなかった。それは、多分、糸満の漁師たちが大いに海洋を動き回って漁をしていた、かなり遠くまで勇敢に出かけて仕事をした、などという話が自分の頭に濃厚に刷り込まれてしまっていたからではないだろうか。あるいはまた、農業方面に関しても、薩摩からの収奪、サトウキビを作らされた等の話ばかり頭に染みこんでいた。そんな自分は、近世の琉球国が農業を奨励し、農村の土台確立を旨としていた、そしてわがふるさと球磨・人吉の球磨茶が好まれ、薩摩を通して盛んに輸入されていた、と『茶と琉球人』で教えられ、まさに眼から梁(うつばり)がとれる思いだったのである。このたびのこの『琉球沖縄史への新たな視座』は、岩波新書で語られている論点がまたさらに分かりやすく述べられており、近世の琉球を理解しようとする際にはぜひ読まれるべき本だと思う。
武井氏は、「琉球が農業型社会であった証拠は、今の沖縄の年中行事にも残されている。一例をあげたい」として、受水走水(ウキンジュハインジュ)で行われる儀式「親田御願(ウエーダウガン)」のことを紹介している。これは『茶と琉球人』の中にもすでに出てくる話だが、今回の方がもっと詳しく説明されており、興味深かった。
-
沖縄本島の南部に位置する南城(なんじょう)市玉城(たまぐすく)地区には、サトウキビの段々畑が連なっている。ここの、稲作発祥の地という伝承のある受水走水(ウキンジュハインジュ)がたたずむ。今でも地域住民の手によって、旧暦正月の初午の日には、「親田御願(ウエーダウガン)」と呼ばれる豊作を願う田植えの儀式が行われている。
なんでも、その「受水走水」を訪れる前には、いくつか拝所を廻るのだという。そして、受水走水では、井泉に手を合わせ拝んだりした後、田植えに臨む。それが終わると別の広場に移って、立ったまま手を合わせ、「三十三拝」を行い、それが済んだら参加者全員で御神酒を飲んで、重箱に盛られた料理を口にするのだそうだ。こうした儀式の話を読むと、わたしなどついつい現地へ赴き、実際に玉城市へ出かけて「親田御願(ウエーダウガン)」を見学したい衝動に駆られてしまうほどだ。 現地の住民の一人幸喜正寿(こうき・まさとし)さんは、かつてそこらは棚田で満ちていた、二期作が営まれる棚田を見下ろすと、田に張られた水が光って眩しいほどだった。さらに、田んぼには、フナ、ウナギ、カニ、タニシなどの生き物もいた、ウナギやカニは「何よりもご馳走だった」と著者に語ってくれたそうだ。こうした話などは、かつて昭和40年代あたりまで日本本土のあちこちで見られた、実に懐かしくて潤いのある農村風景だな、と思う。そうした風景が、かつてあちらでも充分に見られたのである。
そして、それと同時に著者の歴史研究者としての立ち位置についても今度の本で知らされた。武井氏は、大学卒業後、平成7年(1995)に千葉敬愛高等学校の教師となった。熊本県の方に職を得たかったものの、あの頃教員志望者にとっては就職氷河期であったためできなかったそうだ。そういえば、当時、若い人たちはまことにかわいそうであったのだ。氏は、次いで4年後に東京学芸大学教育学部付属高等学校大泉学舎に異動。平成20年(2008)になって、琉球大学法文学部(現国際地域創造学部)の准教授として採用され、沖縄へ移住したのだという。
ところが、氏は「沖縄でたった一人の日本近世史の研究者」ということになるのだそうだ。その間の事情を、武井氏自身は「沖縄で日本近世史に〃光〃があたらないのは、沖縄がたどった歴史に起因している」という点に絞って説明してくれている。かつて、沖縄は琉球国であった。だから、当然、歴史研究は「琉球史」が主となるのであり、沖縄から見れば「前近代の日本史は外国史のようなもの」ということになる。そのような学問風土のところへ日本近世史の専門家として赴いたのであるから、これは実に孤独なことではなかろうか。そうした武井氏の立ち位置について、大いに同情が湧いた。ただ、「孤独」であっても、「孤立」してはいないようだ。なぜなら、大学の同僚で琉球史研究の第一人者である高良倉吉氏から、近世琉球では武井氏の故郷で製されていた球磨茶が薩摩を通して輸入され、よく飲まれていた、と教えられた。豊見山和行という同僚からも同様のことを聞いたので、こうしたことが武井氏の視野を大いに広げたことになる。そして、興味関心を抱き、追究した結果が『茶と琉球人』に結実したのだというから、沖縄の学者たちは大いに心が広い。
なんだか、大袈裟かも知れないが、読者は一つのドラマを観させてもらったような気分になりはしないか。
武井氏は、また、戦時中、自分のふるさとやその近くに沖縄から本土への集団疎開が行われたという事実にも関心を寄せて行く。そのことは前半の「琉球沖縄史を見る眼――新たな視座を求めて」でも語られているのだが、もっとまとまったかたちのものが巻末の「新崎千代――人吉球磨に生きた沖縄女性」である。人吉市九日町の新崎(あらさき)たばこ店の新崎千代(ちよ)さんは、沖縄の出身。沖縄で生まれて、育ち、小学校教員となった。同じ教員であった新崎寛直(かんちょく)と結婚し、3男2女をもうけた。順調に見えたが、やがて戦争が始まり、千代さんは家族で九州へ疎開。初め鹿児島、次いで宮崎、そして終戦前の昭和20年(1945)6月中旬からは人吉で暮らすこととなったそうだ。ところが、終戦直前に夫が病死。一緒に暮らしていた祖母もそれを追うように帰らぬ人となってしまい、新崎千代さんは子ども5人とともに母子家庭を営むこととなった。人吉市内にも他に沖縄からの疎開者たちがいて、お互い助け合ったようだが、5人の子を抱えての母子家庭、それはもう大変なことであったろう。だが、千代さんは人吉市内の最も繁華な界隈である九日町に住んで、雑貨商を営み、やがて古物商、衣料品店を構えた。そして、もっと後になってからはたばこ店をするのである。子どもたちは無事に育ち、特に三男は会社員をやっているうちに「浅川純(あさかわ・じゅん)」とのペンネームでオール読物推理小説新人賞を受賞して、作家となった。 そして、千代(ちよ)さんは、平成16年(2004)4月21日に99歳で亡くなったのだそうだ
人吉市九日町の大通りは、わたしなども子どもの頃から買いものやら球磨川へ遊びに行くためやら、しょっちゅう行き来した。田舎町の中で、最も賑やかな界隈であったのだ。無論、新崎たばこ店も見慣れた風景の一つであった。中学校1年生の時に担任してくれた先生は新崎家の長女の方と結婚されたから、2人で仲良く店番しておられるのを見かけたこともある。そういったことが懐かしく思い出されるが、しかしその店にこのような波乱に満ちた生涯が秘されていたとは、迂闊にも知らなかった。
人吉だけでなく、わたしが現在住んでいる八代市でも、日奈久温泉には沖縄からたくさんの人たちが疎開してきていた、と聞いている。つい最近も、沖縄県南風原町在住の詩人・高良勉(たから・べん)氏が、自分の本名・高嶺朝誠(たかみね・ちょうせい)で発表したレポート「学童疎開調査報告」を送ってくださったので、八代市坂本町や日奈久町での疎開の詳しいことを勉強することができたばかりであった。もっと更に知っておかねばならぬな、と、つくづく思う。
ともあれ、このたびの一冊『琉球沖縄史への新たな視座』を読んで、また改めて武井弘一氏の歩んでいる道のことを知らされた思いである。今後の研究・著述がさらにもっと豊かな結実を得られることを、心から期待したい。