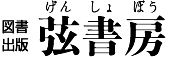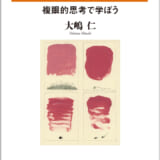前山光則
近頃、松尾定行・著『昭和百年 おもいでの夜行列車――遠くまで、喜びの朝へ』(彩流社)という本を読んで、面白かった。そして、自分でも学生時代の色々な思い出が記憶の底から甦ってきた。
この本でまず教えられたことがある。それは、「夜汽車」と「夜行列車」は違うものだ、ということ。国語辞典や広辞苑などではこれを区別しておらず、ただ単に夜汽車は「夜走る汽車。夜行列車」(旺文社『国語辞典』)、「夜間運行する列車。夜行列車」(岩波書店『広辞苑』第四版)というふうに、両者を同じものとして取り扱っている。だが、今度読んだ本の著者に言わせれば、それは実は違っており、「夜汽車」は単に「夜間に走る汽車」。これに対して「夜行列車」は、朝日が昇ってもまだ走りつづけるのである。つまり、「日付をまたいで半日前後走る列車」が「夜行列車」なのだそうだ。
昭和時代に旅行客たちを乗せて走った「特急北斗星1号」、「急行津軽」「急行能登」、「急行アルプス」、「急行銀河」「急行だいせん2号」等々の夜行列車がこの本には登場する。九州の人間にとっては「急行/特急安芸」(東京~広島/新大阪~下関)、「急行かいもん(門司港~伊集院)」、「カートレイン(汐留~東小倉)」が出てくるので嬉しい。しかも詳しく紹介してあり、読んでいて愉しい本であった。
最も興味深かったのが、著者自身の学生時代の北海道旅行について語った部分である。かつて、北海道にはドン行つまり鈍行、各駅停車の夜行列車があったそうだ。著者は函館始発滝川行きの列車に23時51分、乗車しているのだが、ガタゴト揺られているうちに、
「堅いシートに腰かけて、窓枠あたりに首をまかせ、しばらく夢うつつの空間をさまよう。ふと現実に戻ったのか、あらぬ自問自答が浮かぶ。――この列車、そして自分は、いったいどこから来て、どこへ行こうとしているのか? ここはどこ? 私はだれ? しばらく間をおいて――私はひとり。ドン行列車で最果てへ行こうとしている、との答え。本当に?」
と一人旅の孤独感を記している。そのようにしてドン行列車に揺られるうちにいつしか眠るのだが、ふと目覚めたらニセコ駅だったそうだ。すでに夜が明けており、「もうすっかり明るくなっていて、あたり一面みどりの海だ。それも、萌え出たばかりの新緑である」と記している。やはり、北海道は素敵なところなのだ。孤独な旅ではあるものの、しかしその孤独感こそがまた若いうちにしか体験できない、かけがえのない旅情だったかと思われる。
それにしても、このドン行夜行列車は、「堅いシート」に腰かけたまま揺られなくてはならぬのだから、さぞかし大変だったろうと思う。「しばらく夢うつつの空間をさまよう」のは、多分、熟睡できていなかったわけだろう。乗客たちは、長時間揺られていくうちに、堅い座席に苦しめられたはず。尻が痺れてしまい、なかなか眠気も訪れてはくれなかったのではないだろうか。大変だったろうな、と同情してしまう。
それというのも、最近、八代駅前の行きつけの喫茶店でマスターと雑談していて、たまたま学生時代の思い出話しが始まったわけである。わたしよりも3歳上のマスターは京都で4年間の大学生活を送っているのだが、夏休みや冬休みで八代に帰って来たり、京都へ戻ったりした思い出を語ってくれた中で、
「あの頃は、寝台列車なんかに乗る金はないし、普通の急行列車で揺られて京都まで行ったもんだ」
懐かしそうに呟いた。そう、確かに昭和40年代、鹿児島本線・山陽本線・東海道本線をまたいで行き来する特急や急行があった。それらはすべて、「夜行列車」であった。そして、裕福な家の者は寝台特急列車で快適に、ゆったりと行き来できたであろうが、そうでない場合、座席に座ったままで眠らなくてはならなかった。
「だから、な、尻が痛くなりおったったいなあ」
とマスターは顔をしかめた。
「そして、座っとるうちにゃあ、尻の感覚がなくなってしもうてなあ……」
マスターがそのように思い出話をするのを、コーヒー啜りながら、うんうん、分かりますよ、そぎゃんだったですなあ、とすっかり同情し、相づち打ちながら聞いたのだった。
ただ、マスターは八代駅から夜行列車に飛び乗って、京都までの旅で済んだ。だから、わたしに言わせてもらえば少しばかり楽な汽車旅行だったわけである。
わたしは東京で学生生活を送ったが、東京へ出るにはまず人吉から八代まで1時間ほどかけて出て来なくてはならなかった。そして、八代からは「桜島号」とか「霧島号」とか名のついた急行や特急に乗り換えて、東京までガッタンゴットンと揺られて行くのだった。寝台車に乗るにはそれだけの料金を払わねばならなかったから、我慢するしかなかった。
あの頃、八代・東京間は急行列車で約22、3時間、特急に乗ったら16、7時間だったろうか。ちなみに、京都までの旅行者たちはこれより7、8時間少なくて済んでいた。そう、喫茶店のマスターが京都までで汽車旅を終えることができたのに対して、東京で学生生活をしていた者たちは、もっともっと長く座席に座っていなくてはならなかったのである。マスターは「尻の感覚がなくなってしもうてなあ……」と言ったが、それはつまり尻が痺れてしまうわけだ。だが、東京に着くまでには、尻が痺れるなどというレベルではない、痺れすらマヒしてしまうほどに疲弊してしまっていた。通路に座り込んだり、長々と寝てしまう人もいたものであった。若い頃だからあのような長時間の乗車に耐え得たけれども、今、同じことをやってみろと命じられても到底ダメだろう。
ただ、夜行列車での旅はそのようにしんどいだけで終始したわけでもなかった。乗客同士、初めのうちこそ会話もなく静かな状態だが、時間が経つと次第に言葉を交わすようになる。やがては話が弾んで、結構仲良く楽しくガタゴト、ガタゴト揺られながら東京までの長時間を過ごしたものであった。これが寝台列車だと、互いの触れあいは、結構生じることはあるものの、ずいぶんと少なかったのではないだろうか。
そういえば、東京から帰省する際に、山口県あたりで朝になっていた。すると、「アサー、アサー」とアナウンスが聞こえてくるのだった。これには毎度可笑(おか)しくってしかたなかった。逆に東京へ上って行く際には、もう夜になっているにもかかわらず「アサー、アサー」。だから、なんだかズッコケてしまう。それというのも、実は、山口県の山陽小野田市に「厚狭(あさ)」という駅があるのだ。厚狭は、結構大きな駅である。
ともあれ、『昭和百年 おもいでの夜行列車――遠くまで、喜びの朝へ』を読んで、あの頃の尻が痺れきってしまったことや厚狭駅の思い出などが久しぶりに生まなましく蘇ってきた。
今時の人吉や八代の若い人たちは、長距離の旅をする際に鉄道を使うことはあまりないだろうと思う。というか、東京へ行くには新幹線を利用するはず。いや、というより、今時は飛行機で、国内どころか外国へアッという間に飛ぶような旅感覚が身についてしまっているのではないだろうか。わたしたちの夜行列車にまつわる思い出を聞かされても、若い人たちは、きっと「なんだか古めかしい昔の話だなあ」という程度の印象しか持たないだろう。
でも、夜行列車で長距離を行き来したのは、スンナリと楽チンな旅をするよりもずっと印象深いものだったのだよなあ、あれはあれで充実した旅だったのだゾと、この『昭和百年 おもいでの夜行列車――遠くまで、喜びの朝へ』を読んでしみじみと思った。そう、実に忘れ得ぬ旅だったのだ。
2025・11・26