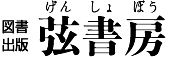前山光則
最近、ある文化団体から、俳文芸についての自分の考えを喋ってほしい、との命が下った。自分は『山頭火を読む』という本を書いたことはあるものの、俳句については全くの素人だ。気の利いた話をする能力は持ちませんよ、と言ったのだが、構わんから気楽にやってくれ、とのことであった。
句作活動を熱心にやっていらっしゃる人たちの前で、わたしなどがちゃんとした俳句論などできるわけがないのである。ただ、門外漢は門外漢なりに気楽なお喋りをすれば良いのかな、と、開き直りの気持ちも湧いてきた。そしたら、ええい、笑われても構わないだろう。気が楽になった。
わたしが五七五という短文芸に少々興味を抱いたのは、高校生の頃であった。教科書に載っている以外では、上村占魚(うえむら・せんぎょ)という人に惹かれた。
「上村占魚」という名が出されても、今はもうあまり知られていないのではないだろうか。この人は、大正9年(1920)、人吉市紺屋町の鰻料理屋に生まれている。本名、武喜である。熊本市立商工学校を卒業後、上京し、東京美術学校(現在の東京芸術大学)で蒔絵(まきえ)を学んでいる。だから、この人は蒔絵師なのだ。俳句の方は高浜虚子に師事し、メキメキと頭角を現した。やがては自身で俳誌「みそさざい」を創刊し、主宰し続けるのである。東京都東村山市に居住し、著書には句集『鮎』『球磨』『上村占魚全句集』、エッセイ集『沖縄の海を歩く』等、多数ある。つまりは、専門の蒔絵の方よりもむしろ俳人として名が知られたことになる。平成8年(1996)2月29日、76歳で死去している。
人の顔見つつ食べゐる夜食かな
友死すと掲示してあり休暇明け
一茶忌や我も母なく育ちたる
ふるさとは山をめぐらし水涸(か)るる
酒のむときめて押したり萩の門
ふるさとや粗にして甘き草の餅
虎落笛(もがりぶえ)ねむれぬ病(やまひ)我にあり
日脚伸ぶ雪ある山になき山に
本丸に立てば二の丸花の中
火の国の肥後に生ひ立ち裸かな
火山灰(よな)曇りしてゐる阿蘇やほととぎす
肌ぬぎの乳房ゆたかに湯もみうた
ふるさとは朱欒(ざぼん)の市(いち)の頃なれや
黴の書に占魚不換酒(ふかんしゅ)の印(いん)存す
白根かなしもみづる草も木もなくて
1句目「人の顔見つつ食べゐる夜食かな」は、昭和12年(1937)の作である。つまり、作者はまだ17歳であったことになるが、他人の家に住み込んで生活している頃の肩身の狭さが表現されている。占魚氏は天才肌だった、と言って良いのではないだろうか。
基本的にはこの人は高浜虚子に学んでおり、客観写生、ホトトギス流の句作法を旨としていたと思う。2句目「友死すと掲示してあり休暇明け」、4句目「ふるさとは山をめぐらし水涸(か)るる」、8句目「日脚伸ぶ雪ある山になき山に」、12句目「肌ぬぎの乳房ゆたかに湯もみうた」などにはそのような傾向があるのではないだろうか。
ただ、客観写生におとなしく収まっていたわけでなく、7句目「虎落笛(もがりぶえ)ねむれぬ病(やまひ)我にあり」は自身のことを吐露する句である。あるいは、9句目「本丸に立てば二の丸花の中」、これは故郷・人吉城址での作だが、実はあそこの二の丸に桜の木は昔も今もありはしない。「花」つまり桜がいっぱい咲いているというのは、全くのフィクションなのである。あるいは、最後の句「白根かなしもみづる草も木もなくて」、これは「白根かなし」などと主情的だ。つまりは、ただただ虚子流の句作法をなぞっていたわけでなく、客観写生を標榜しつつ、時により場合により、かなり柔軟に自身を表現しつづけた俳人だったと言ってよい。
わたしは上村占魚氏の生家のすぐ近くで生まれ育っているので、高校時代に学校の図書館でこの人の句集に接してその存在を知った時、驚いたし、たいへん新鮮な親しさを覚えた。だから、影響を受けなかったはずがないと思っている。
もう1人、忘れられない「俳人」がいる。それは、寺山修司氏だ。この人は、昭和10年(1935)、青森県弘前市の生まれである。青森高校在学中から文芸に目覚め、早稲田大学教育学部に進んで後、本格的に文芸活動を始める。在学中、短歌作品「チェホフ祭」50首にて「短歌研究」新人賞を受賞。以後、短歌・俳句・詩・エッセイ・小説・戯曲等を盛んに発表し、大いに世間から注目されて行く。劇団「天井桟敷」を主宰して活躍したが、昭和58年(1983)、47歳にて逝去する。多才ぶりを発揮して活躍し、疾駆し、しかしながらアッという間にいなくなってしまったのであった。
人吉から東京へ出て行き、法政大学の第二部つまり夜間部に籍を置いて生活していた頃、この寺山修司という存在を知った。いや、それが、在学中、雪華社という小出版社の編集部で1年半ほど働いたことがあるのだが、そこの一番売れる刊行物が寺山修司編の『男の詩集』であった。ボードレールや萩原朔太郎らの名詩が載っているだけでなく、三橋美智也や春日八郎等がうたう流行歌の歌詞などまでも収録されており、実に異色のアンソロジーだった。とにかく、好評であった。
寺山氏は、当時、「天井桟敷」という劇団を率いていた。いわゆるアングラ劇団の中では、代表格だったのだ。そうした催しの場で自身の著書も販売していたので、時折り会社に「『男の詩集』を販売するから、20冊、会場に持って来てほしい」などと連絡が来ていた。御自宅に何十冊か届けたこともある。だから何回もこの人には会っているが、詳しく話を伺ったこともなければ、著作を読んだこともなかった。正直、当時はまださほど興味がなかったのであった。ただ、この人の短歌「マッチ擦(す)るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」、これだけは凄いな、と舌を巻いた覚えがあったのだが、それが、あるとき何かの本に寺山氏の俳句が載っていた。ビックリした。
小春日や病む子も居たる手毬唄
シベリアも正月ならむ父恋し
ちゝはゝの墓寄りそひぬ合歓(ねむ)のなか
葱(ねぎ)坊主どこをふり向きても故郷
春の銃声川のはじまり尋(と)めゆきて
文芸は遠し山焼く火にそだち
林檎の木ゆさぶりやまず逢いたきとき
便所より青空見えて啄木忌
花売り車どこへ押せども母貧し
わが夏帽どこまで転べども故郷
方言かなし菫(すみれ)に語り及ぶとき
他郷にてのびし髭剃る桜桃忌
かくれんぼ三つかぞえて冬となる
母の蛍捨てにゆく顔照らされて
酢を舐める神父毛深し蟹料理
占魚氏の句とはまったく違って、高浜虚子の影響などカケラもない代物ではないだろうか。4句目「葱(ねぎ)坊主どこをふり向きても故郷」や「方言かなし菫(すみれ)に語り及ぶとき」等、この人の詠む「故郷」は絶対に九州人には分からない雰囲気を有している。津軽という北国で、雪のしんしん降り積む中から生み出された独特の詩情だ、と驚嘆した。
そして、なにより7句目の「林檎の木ゆさぶりやまず逢いたきとき」は衝撃的だった。自分の好きな女の子に会いたくてしかたない、という熱情を「林檎の木ゆさぶりやまず」と詠ってあるのにはビックリしてしまった。俳句って、こんなにも自由に自身を表現してかまわないのだ。写生を重んじるホトトギス派とは明らかに一線を画した作品群、作者の青春が熱く豊かに表現されており、圧倒された。それと、「ちゝはゝの墓寄りそひぬ合歓(ねむ)のなか」「花売り車どこへ押せども母貧し」「母の蛍捨てにゆく顔照らされて」と詠んだ句などには、意図的に寺山流のフィクションというか、物語性が込められていると思う。ちなみに、「ちゝはゝの墓」とあるが、実際にはこの人の母親は作者が亡くなった後もずいぶんと長生きをしている。
さらに、「かくれんぼ三つかぞえて冬となる」「母の蛍捨てにゆく顔照らされて」「酢を舐める神父毛深し蟹料理」、こういった作品は「俳句」という枠を越えている。一句一句が、それぞれショートストーリーなのではないだろうか。
何にしろ、寺山修司の俳句は単なる「花鳥諷詠」ではない。モダンであり、しかし同時に土俗的でもあり、虚構もずいぶんとほどこされており、独特の世界だと思う。
わたしは、若い頃、この上村占魚と寺山修司というまったく傾向の違う俳人に接して、両方から結構影響を受けてしまった、と思っている。
――と、まあこのようなことを喋らせてもらった。喋りながら、なんだか破れかぶれであるなあ、という気持ちであった。
はてさて、聴いてくれた人たちはどのように受け止めてくださったであろうか。苦笑いする人も結構いたような気がしてならない。この前山という男、まったく支離滅裂に俳句を読んできたのであるなあ、などと感じた人が多かったのではないだろうか。
だけれども、ともあれ、そのようにして青春を過ごし、老いて、現在に至っている。自分は、否定しようもなくそのようにして時を過ごしてきたのだ。占魚さんも寺山氏も共に独特の世界を持つ俳人であったと思うから、今でも変わりなく尊敬している。
2025・8・1