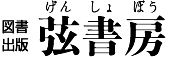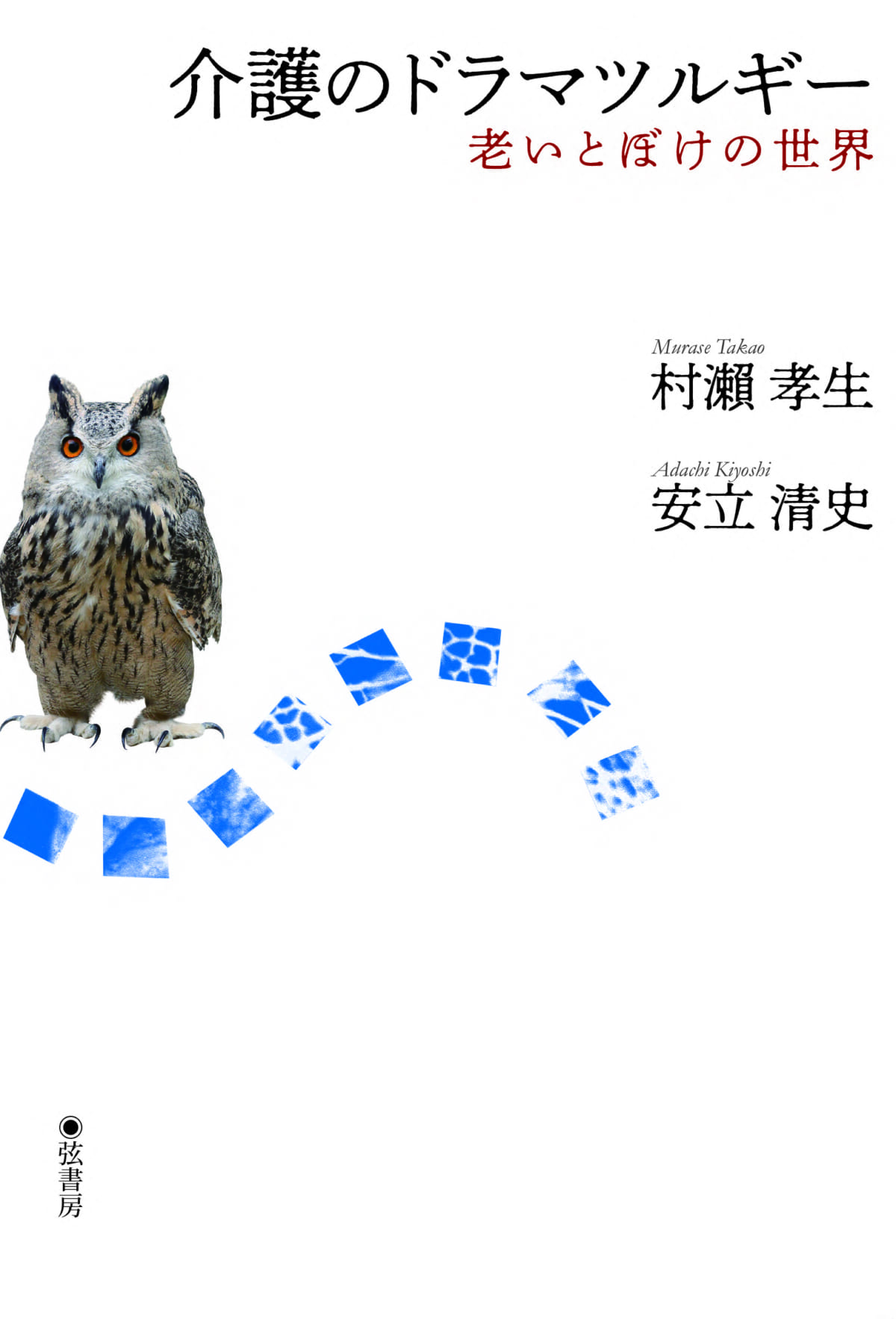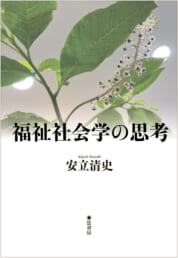介護の現場で日々の営みから「人間」を考え続ける村瀨孝生氏と、九州大学で福祉社会学やボランティア・NPO論を研究してきた安立清史氏の二人が、本当に必要とされている介護について語る。老いてゆく人とそれを見守る人が織りなす言葉と言葉、体と体、体と言葉。老いの前では、言葉は無力になるという現実を前に、その掛け合いをひとつの劇場的なもの(ドラマツルギー)としてとらえ、「宅老所よりあい」のエピソードを新たな視点から考える。◆この本のどこかに介護の〈いま、ここ〉で必要なヒントが必ず見つかります。
はじめに――村瀨孝生と「宅老所よりあい」の世界
Ⅰ
心を手放す …………………………………………………………………村瀨孝生
心を洗面所に置く
トイレでの苛立ち
息が合わない
言葉を所有する
手段化される言葉
体に委ねる
目的を達成しない言葉
介護にとって「ことば」とは何か ………………………………………安立清史
一人に向けて
命名をめぐるドラマ
嘘ですが、マジでした
名前はまだない/名前はもうない
ストレイ・シープ(迷える羊)
Ⅱ
もうひとつのこの世 ………………………………………………………村瀨孝生
底辺
新聞を支える人たち
支配
介護と社会
衰退の拒絶
機械文明の限界
実感に存在する私
拠って立つ大地
こころが離れていくときのドラマ………………………………………安立清史
隠喩としての病
Nさんのロシア行き
「科学的介護」と「野生の介護」
「よりあい」の逡巡と原点回帰
「ディメンシア」と「認知症」の間で
私の手放し
Ⅲ
成仏と供養 ………………………………………………………………… 村瀨孝生
立派な言葉
生まれてはいけない言葉
崩壊と再生
申し送り
負の力
負の言葉と私たち
夢幻能の一夜…………………………………………………………………安立清史
「お婆」を探すお婆さん
介護という夢幻能
石をパンに変えてみよ
新人さん、迫真の現場報告
「よりあい」が自分たちを発見する瞬間
タブーに触れる
カオナシとハツさんの部屋
夢幻能を通り抜ける
Ⅳ
「私」の手放し……………………………………………………………… 村瀨孝生
いのちの笑み
脳トレ
降りてくる
「私」の手放し
老人性アメイジング ………………………………………………………安立清史
こんなになって……
どうして・どうして・と考えている人たち
受け入れられないことを受け入れる――死の受容・老いの受容
老人性アメイジング
私を手放す
戦わない・戦い方/乗り越えない・乗り越え方
Ⅴ
まるごとのいのち ………………………………………………………… 村瀨孝生
「死にたい」でも「生きたい」でもない境地へ
体同士の交流
自意識から解放される
勝手にやってくる希望 …… ………………………………………………安立清史
夜汽車と銀河鉄道
「宅老所よりあい」の軌跡
底辺にふれる
「今、ここ」の世界
しない・を・する
永遠と一日
勝手にやってくる希望
村瀨 孝生
特別養護老人ホーム「よりあいの森」「宅老所よりあい」「第2宅老所よりあい」の統括所長。
1964年生まれ。東北福祉大学卒業後、出身地である福岡県飯塚市の特別養護老人ホームに生活指導員として勤務。その後、福岡市にある「第2宅老所よりあい」に入職し、現在に至る。
著書に、『おしっこの放物線――老いと折り合う居場所づくり』(雲母書房、2001)、『ぼけてもいいよ――「第2宅老所よりあい」から』(西日本新聞社、2006)、『認知症をつくっているのは誰なのか――「よりあい」に学ぶ認知症を病気にしない暮らし』(共著、SBクリエイティブ、2016) 、『増補新版 おばあちゃんが、ぼけた。』(新曜社、2018) 、『あきらめる勇気――老いと死に沿う介護』(ブリコラージュ、2010)、『看取りケアの作法――宅老所よりあいの仕事』(雲母書房、2011)、『ぼけと利他』(共著、ミシマ社、2022)、『シンクロと自由』(医学書院、2022)など。
安立 清史
1957年生まれ。九州大学名誉教授。「超高齢社会研究所」代表。専門は、福祉社会学、ボランティア・NPO論。著書に、『福祉の起原』(弦書房、2023)、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房、2022)、『21世紀の《想像の共同体》―ボランティアの原理 非営利の可能性』(弦書房、2021)、『超高齢社会の乗り越え方―日本の介護福祉は成功か失敗か』(弦書房、2020)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会、2008)、『介護系NPOの最前線―全国トップ16の実像』(共著、ミネルヴァ書房、2003)、『ニューエイジング:日米の挑戦と課題』(共著、九州大学出版会、2001)、『高齢者NPOが社会を変える』(共著、岩波書店、2000)、『市民福祉の社会学―高齢化・福祉改革・NPO』(ハーベスト社、1998)など。
| 福祉の起原 | |
| 福祉社会学の思考 | |
| 超高齢社会の乗り越え方 | |
| ボランティアと有償ボランティア | |
| 21世紀の《想像の共同体》 |