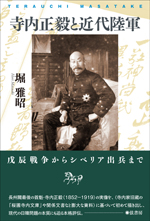前山 光則
2月に、或る催しの中で種田山頭火について講演することになっている。だから、今、『山頭火全集』やら村上護著『種田山頭火』やら自分の書いた『山頭火を読む』等を本棚から引っ張り出し、読み直している。
そんな中で、ふと思ったことがある。それは、山頭火が折りに触れて作った短歌についてである。村上護著『種田山頭火』から引いてみるが、
美しき人を泣かして酒飲みて調子ぱずれのステヽコ踊る
酒飲めど酔ひえぬ人はたヾ一人、欄干つかみて遠き雲みる
大正2年(1913)1月発行の回覧雑誌「初凪」に載った作品のうちの2首で、同誌の雑信には「旧作」と記されていたそうである。山頭火は明治39年(1906)に佐藤サキノと結婚しており、「美しき人」とはそのサキノであるに違いない。結婚生活がうまくいっていない状況が窺える内容だ。同じく大正2年2月には短歌回覧雑誌「四十女の恋」第1号にも参加。自由詩1編と短歌6首を発表した。その中から2首。
わが心たヾ何となう物足らで愚痴になりゆくことのさびしさ
愛し得ねど離れ得ぬ世の二人なれば言葉すくなに酒あほりをり
これも、妻との間がうまくいっていないということが明らかである。ちなみに、この時期の山頭火は荻原井泉水の自由律俳句に共鳴し、その俳誌「層雲」に参加している。
種田家が破産し、妻子を連れて熊本へやってくるのが大正5年(1916)である。翌々年は、弟の二郎が故郷の山中で自殺する。その時の歌、
今はただ死ぬるばかりと手を合せ山のみどりに見入りたりけむ
弟は養子先から離縁された果てに死を選んだのだが、その「離縁」は種田家の破産と密接に絡んでいた。山頭火として、弟の死は痛切なものがあったのだ。さて、それから大正8年頃、友人の茂森唯士に書いてやったという歌がある。
酔ひしれて路上に眠るひとときは安くもあらん起したまふな
これなど、飲んべえ山頭火の面目躍如、酒から離れ得ぬ自身の心境を如実に示した作である。そして、つまりこれは熊本に来てから詠んだのであるが、山頭火は熊本では結構地元の文学関係者との交友が生じている。俳句だけでなく、地元歌人たちと交わり、歌会などにも参加するし、地元新聞に歌が載ったりしている。本領である自由律俳句からしたらほんのちょっとの数でしかないものの、山頭火は折りに触れて短歌も作っていた人なのである。
こういうことを辿りながら、山頭火は歌人としては「自由律」をやっていないのだなあ、と、ふと思ったわけである。
定型の枠から身を剥がして表現してゆく試みは、なにも河東碧梧桐や荻原井泉水や山頭火等の俳人たちだけが手がけたわけでなく、短歌の世界でも行われた経緯がある。ものの本によれば、明治時代の終わり頃から大正の始めごろにかけて島木赤彦や斎藤茂吉の作に自由律の試みが見られるそうだ。そして、若山牧水も積極的に詠んだ時期がある。
眼の見えぬ夜の蝿ひとつわがそばにつきゐて離れず、恐ろしくなりぬ
手を切れ、双脚(もろあし)を切れ、野のつちに投げ棄てておけ、秋と親しまむ
これは大正元年刊の第五歌集『死か芸術か』から2首だけ引いてみた。1首目は「破調」といった趣きである。しかし、2首目の方はこれだけ5・7・5・7・7の型を崩してあるからには「破調」どころでなく、「自由律」とみなすべきであろう。翌年刊行の第六歌集『みなかみ』にも自由律が多くて、
納戸の隅に折から一挺の大鎌あり、汝(なんぢ)が意志をまぐるなといふが如くに
思ひつめてはみな石のごとく黙(つぐ)み、黒き石のごとく並ぶ、家族の争論
さうだ、あんまり自分のことばかり考へてゐた、四辺(あたり)は洞(ほらあな)のや うに暗い
大正に入ってすぐの頃の牧水は20歳台を終えようとしていた。園田小枝子との大恋愛に破れ、太田貴志子と出会って結婚したのもつかのま、故郷・宮崎県の坪谷では父が倒れた。家を継ぐべきか否か、責め立てられ、大いに悩んでいた。そのような時期に、かなり積極的に自由律で短歌創作を試みたのであった。もっとも、長くは続かず、直きにまた定型の方に戻る。
というふうに、短歌の世界にも自由律の動きがあったので、山頭火がそれを知らなかったはずはない。試みそうなものであるが、なぜかその形跡はまったくない。不思議というか、おもしろいというか、ともあれ気になったわけであった。
いや、あまり生真面目に考える必要はなかろうと思う。山頭火は俳句創作には自身の生涯を賭けるほどに拘ったが、短歌についてはさほど本気でなかった。「余技」に過ぎなかったと言えよう。余技であるから、従来通りのやり方をなぞれば、それで事足りたのである。ただし、それにしてもなぜ俳句には本気になり、短歌に対してはさほど拘らなかったのか、という問題が残るだろう。同じ短文芸でも、短歌と俳句では表現する際にそれぞれ固有の必然を有している。――こういうふうになると、難しい課題ではある。