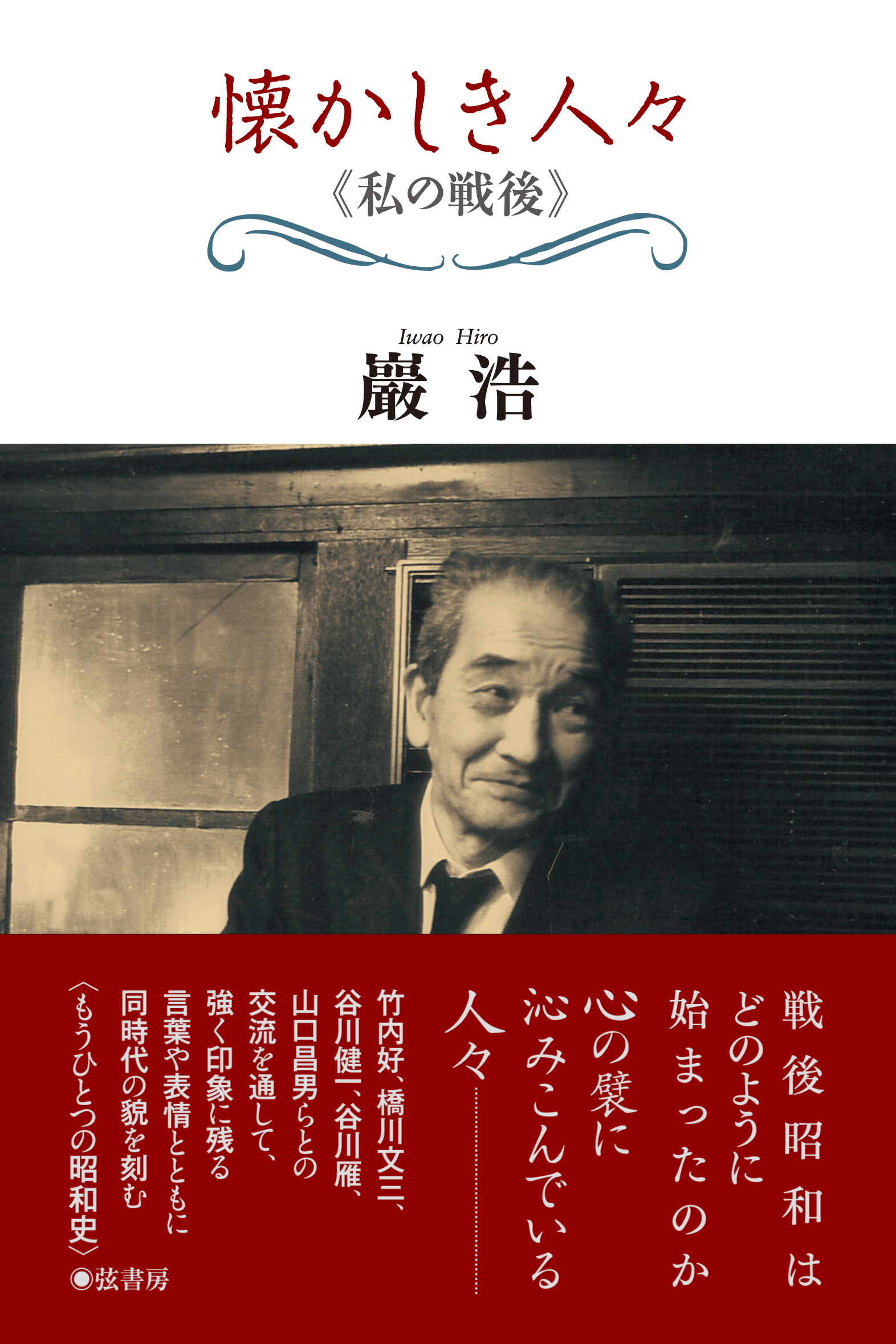前山 光則
暦の上では11月8日が立冬であった。だから、現在もうすでに冬に入っていることになる。昼間はそうでもないものの、夜が来ると結構寒い。ストーブや炬燵に頼りたくなっているが、かろうじてまだ我慢している。
最近読んだ本で、武田博幸著『古典つまみ読み 古文の中の自由人たち』という新書本はとても面白かった。「つまみ読み」などと卑下したようなサブタイトルが付してあるが、いやいや、日本の古典文学に登場する「自由人」たちを次々に紹介し、詳しく論じてあって、たいへん本格的な古典文学論だ。しかも分かりやすい文章である。詳しい説明はすでに或る新聞に書評を書いたから省くが、この本の第一回「宇治拾遺物語」から一番最後の第十四回「良寛全集」に至るまで、そのいちいちが興味深かった。
特に後半の方が魅力的だ。第十二回「徒然草」では、吉田兼好は世間に対してある距離を置いていた、そうして自分自身を保持するように常に努めた、それが兼好法師の生きざまである、だから「徒然草」を何度も読み直すうちに「これぞ自由人」といえる人にようやく出会った気がした、と著者は思ったそうだ。その上で、著者は次のように述べる。
「兼好が三十歳の頃、出家遁世したのは、世をはかなんだわけでも何でもなく、わが自由を確保しようとしてのことだったと私は確信します」
これは、そのままわたしたち現代人の生き方を問うているようなものではなかろうか。
第十三回「山家集」がまた格別だった。西行法師の有名な歌、
さびしさに堪へたる人のまたもあれな庵(いほり)ならべん冬の山里
を引いて、西行は自分と同じく「さびしさに堪へたる人」を求めている。人は、誰もがさびしい。さびしいから、そのさびしさを共有することで互いにつながり合える、という可能性をこの歌には見ることができる、と、著者はそのように西行の名歌を読む。このような西行に共鳴したから松尾芭蕉は「憂き我をさびしがらせよ閑古鳥(かんこどり)」との句を詠んだのだ、と著者は言っており、なるほど、そうか。つい唸ってしまった。これは人と人との結びつきについて、肝心要(かんじんかなめ)のところが述べられているように思えた。
そして、最後の第十四回「良寛全集」。
世の中にまじらぬとにはあらねどもひとり遊びぞわれはまされる
を例に挙げて、著者は一人遊びが好きだった良寛を論じている。身を立て家を興すようなことに自分の力を傾ける気にはなれなかった人、良寛。著者は「羞恥の人であった良寛は、世の束縛を嫌い、身も心も自由を求めてやまなかった」と言い、そしてそのような自分の行為を良寛は「ひとり遊び」と称したのではないか、と、著者はそう見るのである。
著者の言う「自由人」というのは、ものにとらわれない、伸び伸びと自分の生き方のできた人、という程の意味になるであろうか。この本はそのような昔の「自由人」たちの生きた軌跡を紹介してくれており、しかもそれが皆われわれ現代人はどう在るべきなのか、との問いとなって響いてくる。古典は、かねてからは遠い昔のものとして縁遠い気がしていたが、実はそうではない。読み通しながら、ずっと、自分の過ごしている日々について振り返らざるを得ない迫力があった。
この本のおかげで古典作品がとても身近に感じられるようになったなあ、と、ありがたく思う。